|
|
|
| �V��������ǘH��{�݂̑����A�l�������ɔ����Z�p�ҕs���A�ЊQ���X�N�̍��܂�A�ێ��Ǘ��R�X�g�̏㏸�ȂǁA���������Ƃ͂���܂łɂȂ������I�ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���B�����ɑΉ����邽�߁A�ߔN�ł̓f�[�^�̗����p�A�Z���V���O�Z�p�A���u�Ď��A���{�b�g�ɂ��_���AAI ��͂ȂǁADX �����Ƃ������l�Ȏ�g�݂��L�������B
�@2025 �N�U���ɔ��\���ꂽ�u�㉺����DX ���i������v�ŏI���܂Ƃ߂ł͍���̕������Ƃ��āu2027�N�x���܂łɁA�㉺����DX �Z�p�J�^���O�Ɍf�ڂ��ꂽDX �Z�p�Ȃǂ������e�i���X�̕W���I�ȃc�[���Ƃ��Ċ��p����A�䒠�V�X�e�����ɂ��ǘH����d�q�����邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��A��g�݂𐄐i����v�Ƃ��ꂽ�B
�@�����ō���͉��������Ƃ����ʂ��邳�܂��܂ȉۑ���������邱�Ƃ����҂����DX �Z�p�ɂ��āA���łɎ����i�K�ɂ���Z�p�𒆐S�Ɏ��グ�A������DX �̍����W�]����B |
|
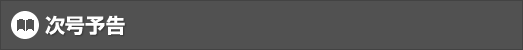 |
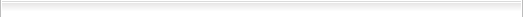 |
|
�@�V�������i�މ������C���t���̐ݔ��̍X���E�X�V��p�͍���������������܂�����A���q����ɂ��l�������ɂ��A�������g�p�������̌����͔������Ȃ��ɂ���B���������Ƃ͒n�����c��ƂƂ��āA�Ɨ��̎Z�̌����Ɋ�Â��A�g�p�������ɂ���Čo�c������Ă��邪�A�����̗\�Z����̐Ԏ���塡�ɗ���Ƃ��낪�傫���B�܂��������g�p���̉���ɂ́A�c��ł̋c����s���̗�����K�v������A�����̃n�[�h���͍����B���̂܂����������葱���A�R�X�g�͑��債�Ă����A�₪�ĉ������o�c���j
�]�����@�ɂȂ肩�˂Ȃ����B
�@�����ō���̓��W�ł́A�������o�c�Ɋւ��āA���̍ŐV�����܂��A�e�����̂������鉺�����o�c�̉ۑ��A�g�p�����莞�̋c�������Z���Ή��Ƃ�������M�̍H�v���̂ق��A�ǂ̂悤�ɂ��č��ӌ`���̃v���Z�X��}���Ă������̂��A���ۂɎg�p��������s���������̂̎���𒆐S�ɏЉ��B�҂����Ȃ��̉������o�c�̔j�]����B���̕����T��B |
|
|
 |
|



